25. 非同期プログラミングのためのPromise
本章では、Promiseによる非同期プログラミング全般、特にECMAScript 6のPromise APIについて入門します。前の章では、JavaScriptにおける非同期プログラミングの基礎を説明しています。本章で理解できない点があれば、そちらを参照してください。
- 25.1. 概要
- 25.1.1.
then()呼び出しのチェーン化 - 25.1.2. 非同期関数を並列実行する
- 25.1.3. 用語集:Promise
- 25.1.1.
- 25.2. はじめに:Promise
- 25.3. 最初の例
- 25.4. Promiseを理解する3つの方法
- 25.4.1. 概念的に:Promiseベースの関数の呼び出しはブロッキングする
- 25.4.2. Promiseは非同期的に配信される値のコンテナである
- 25.4.3. Promiseはイベントエミッタである
- 25.5. Promiseの作成と使用
- 25.5.1. Promiseの生成
- 25.5.2. Promiseの状態
- 25.5.3. Promiseの消費
- 25.5.4. Promiseは常に非同期である
- 25.6. 例
- 25.6.1. 例:
fs.readFile()のPromisify - 25.6.2. 例:
XMLHttpRequestのPromisify - 25.6.3. 例:アクティビティの遅延
- 25.6.4. 例:Promiseのタイムアウト
- 25.6.1. 例:
- 25.7. Promiseを作成する他の方法
- 25.7.1.
Promise.resolve() - 25.7.2.
Promise.reject()
- 25.7.1.
- 25.8. Promiseのチェーン化
- 25.8.1. 通常の値でQを解決する
- 25.8.2. ThenableでQを解決する
- 25.8.3.
onRejectedからQを解決する - 25.8.4. 例外をスローすることでQを拒否する
- 25.8.5. チェーン化とエラー
- 25.9. Promiseチェーン化のよくある間違い
- 25.9.1. 間違い:Promiseチェーンの末尾を失う
- 25.9.2. 間違い:Promiseをネストする
- 25.9.3. 間違い:Promiseをチェーン化せずに作成する
- 25.9.4. 間違い:エラー処理に
then()を使用する
- 25.10. エラー処理のヒント
- 25.10.1. 運用上のエラーとプログラマーエラー
- 25.10.2. Promiseベースの関数における例外の処理
- 25.10.3. さらに読む
- 25.11. Promiseの合成
- 25.11.1. 手動による計算のフォークと結合
- 25.11.2.
Promise.all()による計算のフォークと結合 - 25.11.3.
Promise.all()によるmap() - 25.11.4.
Promise.race()によるタイムアウト
- 25.12. 2つの有用な追加Promiseメソッド
- 25.12.1.
done() - 25.12.2.
finally()
- 25.12.1.
- 25.13. Node.js:コールバックベースの同期関数とPromiseの使用
- 25.14. ES6互換のPromiseライブラリ
- 25.15. 次のステップ:ジェネレータによるPromiseの使用
- 25.16. Promiseの詳細:簡単な実装
- 25.16.1. 独立したPromise
- 25.16.2. チェーン化
- 25.16.3. 平坦化
- 25.16.4. Promiseの状態の詳細
- 25.16.5. 例外
- 25.16.6. コンストラクタパターンの公開
- 25.17. Promiseの長所と短所
- 25.17.1. Promiseの長所
- 25.17.2. Promiseが常に最良の選択肢とは限らない
- 25.18. 参考:ECMAScript 6 Promise API
- 25.18.1.
Promiseコンストラクタ - 25.18.2. 静的
Promiseメソッド - 25.18.3.
Promise.prototypeメソッド
- 25.18.1.
- 25.19. さらに読む
25.1 概要
Promiseは、非同期計算の結果を配信するためのコールバックの代替手段です。非同期関数の作成者にはより多くの労力を要求しますが、それらの関数の使用者にはいくつかの利点を提供します。
次の関数は、Promiseを介して非同期的に結果を返します。
function asyncFunc() {
return new Promise(
function (resolve, reject) {
···
resolve(result);
···
reject(error);
});
}
asyncFunc()は次のように呼び出します。
asyncFunc()
.then(result => { ··· })
.catch(error => { ··· });
25.1.1 then()呼び出しのチェーン化
then()は常にPromiseを返し、メソッド呼び出しをチェーン化できます。
asyncFunc1()
.then(result1 => {
// Use result1
return asyncFunction2(); // (A)
})
.then(result2 => { // (B)
// Use result2
})
.catch(error => {
// Handle errors of asyncFunc1() and asyncFunc2()
});
then()によって返されるPromise Pの解決方法は、そのコールバックが何をするかに依存します。
- Promiseを返す場合(A行のように)、そのPromiseの解決はPに転送されます。そのため、B行のコールバックは
asyncFunction2のPromiseの解決を受け取ることができます。 - 異なる値を返す場合、その値を使用してPを解決します。
- 例外をスローすると、Pはその例外で拒否されます。
さらに、catch()が2つの非同期関数呼び出し(asyncFunction1()とasyncFunction2())のエラーをどのように処理しているかに注目してください。つまり、キャッチされないエラーは、エラーハンドラが存在するまで渡されます。
25.1.2 非同期関数を並列実行する
then()を介して非同期関数呼び出しをチェーン化する場合、それらは一度に一つずつ順番に実行されます。
asyncFunc1()
.then(() => asyncFunc2());
そうせず、すべてをすぐに呼び出すと、基本的に並列に実行されます(Unixプロセスの用語ではフォーク)。
asyncFunc1();
asyncFunc2();
Promise.all()を使用すると、すべての結果が揃った時点で通知を受け取ることができます(Unixプロセスの用語ではジョイン)。その入力はPromiseの配列であり、その出力は結果の配列で解決される単一のPromiseです。
Promise.all([
asyncFunc1(),
asyncFunc2(),
])
.then(([result1, result2]) => {
···
})
.catch(err => {
// Receives first rejection among the Promises
···
});
25.1.3 用語集:Promise
Promise APIは、結果を非同期的に配信することについてです。Promiseオブジェクト(略してPromise)はそのオブジェクトを介して配信される結果の代役およびコンテナです。
状態
- Promiseは常に3つの相互に排他的な状態のいずれかになります。
- 結果の準備が整う前、Promiseは保留中です。
- 結果が利用可能になると、Promiseは解決済みです。
- エラーが発生した場合、Promiseは拒否済みです。
- Promiseが確定しているとは、「処理が完了した」(解決済みまたは拒否済みのいずれかである)ことを意味します。
- Promiseは正確に一度だけ確定し、その後は変更されません。
状態の変化への反応
-
Promise反応とは、解決または拒否を通知するために、Promiseメソッド
then()で登録するコールバックです。 - Thenableとは、Promiseスタイルの
then()メソッドを持つオブジェクトです。APIが解決の通知に関心しかない場合、Thenableのみを要求します(例:then()とcatch()から返される値、またはPromise.all()とPromise.race()に渡される値)。
状態の変更:Promiseの状態を変更するための操作は2つあります。いずれか一方を一度呼び出した後、それ以上の呼び出しは無効になります。
- Promiseを拒否するとは、Promiseが拒否済みになることを意味します。
-
Promiseを解決することの影響は、何の値で解決するかによって異なります。
- 通常の(Thenableではない)値で解決すると、Promiseは解決済みになります。
- Promise PをThenable Tで解決するということは、Pはそれ以上解決できなくなり、Tの状態(解決済みまたは拒否済みの値を含む)に従うようになります。適切なP反応は、Tが確定したときに呼び出されます(Tが既に確定している場合はすぐに呼び出されます)。
25.2 はじめに:Promise
Promiseは、特定の種類の非同期プログラミング、つまり単一の結果を非同期的に返す関数(またはメソッド)を処理するのに役立つパターンです。そのような結果を受け取る一般的な方法は、コールバックを使用することです(「継続としてのコールバック」)。
asyncFunction(arg1, arg2,
result => {
console.log(result);
});
Promiseはコールバックを処理するより良い方法を提供します。非同期関数はPromise、つまり最終結果のプレースホルダーおよびコンテナとして機能するオブジェクトを返します。Promiseメソッドthen()を介して登録されたコールバックは、結果を通知されます。
asyncFunction(arg1, arg2)
.then(result => {
console.log(result);
});
継続としてのコールバックと比較して、Promiseには次の利点があります。
- 制御の反転がない:同期コードと同様に、Promiseベースの関数は結果を返し、コールバックを介して実行を(直接)継続したり制御したりしません。つまり、呼び出し側が制御を維持します。
- チェーン化が簡単:
then()のコールバックがPromiseを返す場合(例:別のPromiseベースの関数を呼び出した結果)、then()はそのPromiseを返します(これが実際にどのように機能するかはより複雑で、後で説明します)。その結果、then()メソッド呼び出しをチェーン化できます。asyncFunction1(a,b).then(result1=>{console.log(result1);returnasyncFunction2(x,y);}).then(result2=>{console.log(result2);}); - 非同期呼び出しの合成(ループ、マッピングなど):データ(Promiseオブジェクト)を操作できるため、少し簡単になります。
- エラー処理:後で説明するように、Promiseを使用するとエラー処理が簡単になります。なぜなら、再び制御の反転がないからです。さらに、例外と非同期エラーの両方が同じように管理されます。
- クリーンなシグネチャ:コールバックを使用すると、関数のパラメータが混在します。一部は関数の入力であり、他は出力の配信を担当します。Promiseを使用すると、関数のシグネチャはよりクリーンになります。すべてのパラメータが入力になります。
- 標準化:Promise以前は、非同期結果を処理するいくつかの非互換な方法がありました(Node.jsコールバック、XMLHttpRequest、IndexedDBなど)。Promiseを使用すると、明確に定義された標準があります:ECMAScript 6。ES6は標準Promises/A+ [1]に準拠しています。ES6以降、ますます多くのAPIがPromiseをベースにするようになっています。
25.3 最初の例
Promiseの使用がどのようなものかを知るために、最初の例を見てみましょう。
Node.jsスタイルのコールバックを使用すると、ファイルの非同期読み取りは次のようになります。
fs.readFile('config.json',
function (error, text) {
if (error) {
console.error('Error while reading config file');
} else {
try {
const obj = JSON.parse(text);
console.log(JSON.stringify(obj, null, 4));
} catch (e) {
console.error('Invalid JSON in file');
}
}
});
Promiseを使用すると、同じ機能は次のように使用されます。
readFilePromisified('config.json')
.then(function (text) { // (A)
const obj = JSON.parse(text);
console.log(JSON.stringify(obj, null, 4));
})
.catch(function (error) { // (B)
// File read error or JSON SyntaxError
console.error('An error occurred', error);
});
コールバックは依然として存在しますが、結果に対して呼び出されるメソッド(then()とcatch())を介して提供されます。B行のエラーコールバックは2つの点で便利です。まず、エラー処理のスタイルが統一されている点(前の例のようにif (error)やtry-catchを使用する必要がない)。第二に、A行のコールバックとreadFilePromisified()の両方のエラーを1箇所で処理できる点です。
readFilePromisified()のコードは後述します。
25.4 Promiseを理解する3つの方法
Promiseを理解する3つの方法を見てみましょう。
次のコードは、Promiseベースの関数asyncFunc()とその呼び出しを含んでいます。
function asyncFunc() {
return new Promise((resolve, reject) => { // (A)
setTimeout(() => resolve('DONE'), 100); // (B)
});
}
asyncFunc()
.then(x => console.log('Result: '+x));
// Output:
// Result: DONE
asyncFunc()はPromiseを返します。非同期計算の実際の結果'DONE'の準備が整うと、A行で始まるコールバックのパラメータであるresolve()(B行)を介して配信されます。
では、Promiseとは何でしょうか?
- 概念的には、
asyncFunc()の呼び出しはブロッキング関数呼び出しです。 - Promiseは、値のコンテナとイベントエミッタの両方です。
25.4.1 概念的に:Promiseベース関数の呼び出しはブロッキング
次のコードは、非同期関数main()からasyncFunc()を呼び出します。非同期関数はECMAScript 2017の機能です。
async function main() {
const x = await asyncFunc(); // (A)
console.log('Result: '+x); // (B)
// Same as:
// asyncFunc()
// .then(x => console.log('Result: '+x));
}
main();
main()の本体は、何が起こっているかを概念的に、つまり非同期計算について私たちが通常どのように考えているかをうまく表現しています。つまり、asyncFunc()はブロッキング関数呼び出しです。
- A行:
asyncFunc()が終了するまで待機します。 - B行:その後、その結果
xを出力します。
ECMAScript 6とジェネレータ以前は、コードを一時停止して再開することができませんでした。そのため、Promiseでは、コードが再開された後に発生するすべての処理をコールバックに記述します。そのコールバックを呼び出すことは、コードを再開することと同じです。
25.4.2 Promiseは非同期的に配信される値のコンテナ
関数がPromiseを返す場合、そのPromiseは、関数が(通常は)計算が完了したら結果を書き込む空白のようなものです。このプロセスの簡単なバージョンを配列を使用してシミュレートできます。
function asyncFunc() {
const blank = [];
setTimeout(() => blank.push('DONE'), 100);
return blank;
}
const blank = asyncFunc();
// Wait until the value has been filled in
setTimeout(() => {
const x = blank[0]; // (A)
console.log('Result: '+x);
}, 200);
Promiseでは、最終的な値に[0](A行のように)アクセスするのではなく、then()メソッドとコールバックを使用します。
25.4.3 Promiseはイベントエミッタ
Promiseを別の見方として、イベントを発行するオブジェクトと考えることができます。
function asyncFunc() {
const eventEmitter = { success: [] };
setTimeout(() => { // (A)
for (const handler of eventEmitter.success) {
handler('DONE');
}
}, 100);
return eventEmitter;
}
asyncFunc()
.success.push(x => console.log('Result: '+x)); // (B)
イベントリスナー(B行)の登録は、asyncFunc()を呼び出した後に行うことができます。これは、setTimeout()に渡されたコールバック(A行)が非同期的に(このコードの部分が終了した後)実行されるためです。
通常のイベントエミッタは、登録されるとすぐに開始される複数のイベントの配信に特化しています。
一方、Promiseは正確に1つの値の配信に特化しており、登録が遅すぎることに対する組み込みの保護が備わっています。Promiseの結果はキャッシュされ、Promiseが確定した後に登録されたイベントリスナーに渡されます。
25.5 Promiseの作成と使用
Promiseがプロデューサー側とコンシューマー側からどのように操作されるかを見てみましょう。
25.5.1 Promiseのプロデュース
プロデューサーとして、Promiseを作成し、それを介して結果を送信します。
const p = new Promise(
function (resolve, reject) { // (A)
···
if (···) {
resolve(value); // success
} else {
reject(reason); // failure
}
});
25.5.2 Promiseの状態
Promiseを介して結果が配信されると、Promiseはその結果に固定されます。つまり、各Promiseは常に3つの(相互に排他的な)状態のいずれかになります。
- Pending:結果はまだ計算されていません(各Promiseの初期状態)
- Fulfilled:結果が正常に計算されました。
- Rejected:計算中にエラーが発生しました。
Promiseは、fulfilledまたはrejectedのいずれかの場合に確定します(それが表す計算が完了しました)。Promiseは一度だけ確定し、その後は確定したままです。その後の確定の試みは効果がありません。
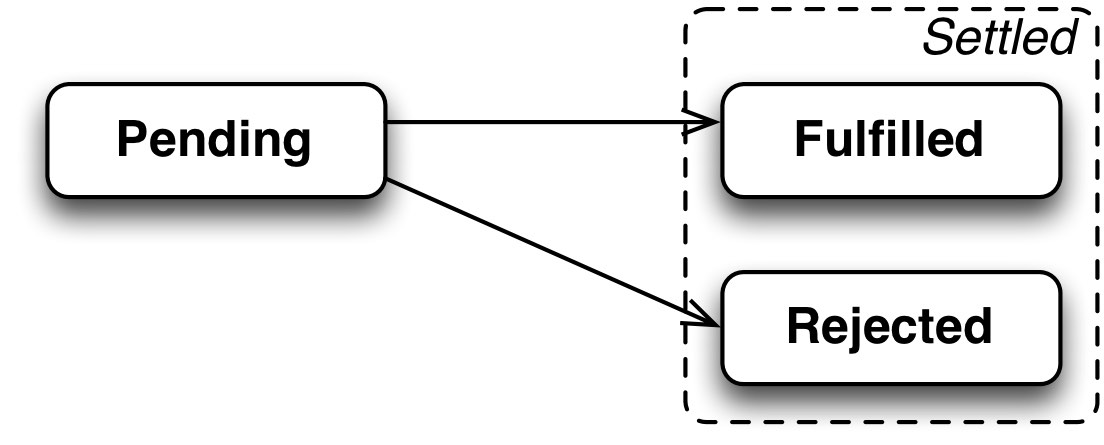
new Promise()のパラメータ(A行から始まる)は、executorと呼ばれます。
- 解決:計算がうまくいった場合、executorは
resolve()を介して結果を送信します。通常は、これによりPromisepがfulfilledになります。しかし、そうとは限りません。Promiseqで解決すると、pはqを追跡することになります。qがまだpendingの場合、pもpendingです。しかし、qが確定すると、pも同じように確定します。 - 拒否:エラーが発生した場合、executorは
reject()を介してPromiseコンシューマに通知します。これにより、Promiseは常にrejectedになります。
executor内で例外がスローされると、pはその例外でrejectedになります。
25.5.3 Promiseの消費
promiseのコンシューマとして、反応(then()とcatch()メソッドで登録するコールバック)を介してfulfillmentまたはrejectionが通知されます。
promise
.then(value => { /* fulfillment */ })
.catch(error => { /* rejection */ });
Promiseが非同期関数(一発の結果を持つ関数)で非常に有用であるのは、Promiseが確定すると、それ以上変化しなくなるためです。さらに、Promiseが確定する前後にthen()またはcatch()を呼び出すかどうかに関係なく、競合状態は決して発生しません。
- Promiseが確定する前にPromiseに登録された反応は、確定するとすぐに通知されます。
- Promiseが確定した後にPromiseに登録された反応は、キャッシュされた確定値を「即座に」受け取ります(それらの呼び出しはタスクとしてキューイングされます)。
catch()は、単にthen()を呼び出すよりも便利(推奨)な代替手段であることに注意してください。つまり、次の2つの呼び出しは同等です。
promise.then(
null,
error => { /* rejection */ });
promise.catch(
error => { /* rejection */ });
25.5.4 Promiseは常に非同期
Promiseライブラリは、結果がPromiseの反応に同期的に(すぐに)配信されるか、非同期的に(現在の継続、現在のコードの部分が終了した後)配信されるかを完全に制御できます。ただし、Promises/A+仕様では、後者の実行モードを常に使用する必要があります。これは、次の要件(2.2.4)でthen()メソッドについて規定されています。
onFulfilledまたはonRejectedは、実行コンテキストスタックにプラットフォームコードのみが含まれるまで呼び出されてはなりません。
つまり、コードは実行完了セマンティクス(前の章で説明)に依存でき、Promiseのチェーン化によって他のタスクの処理時間が不足することはありません。
さらに、この制約により、結果を同期的に返す場合と非同期的に返す場合がある関数を記述することが防止されます。これは、コードが予測不可能になるため、アンチパターンです。詳細については、Isaac Z. Schlueterによる「非同期のためのAPI設計」を参照してください。
25.6 例
Promiseを詳しく調べる前に、これまでの学習内容をいくつかの例で使用してみましょう。
25.6.1 例:fs.readFile()のPromisify
次のコードは、組み込みのNode.js関数fs.readFile()のPromiseベースのバージョンです。
import {readFile} from 'fs';
function readFilePromisified(filename) {
return new Promise(
function (resolve, reject) {
readFile(filename, { encoding: 'utf8' },
(error, data) => {
if (error) {
reject(error);
} else {
resolve(data);
}
});
});
}
readFilePromisified()は次のように使用します。
readFilePromisified(process.argv[2])
.then(text => {
console.log(text);
})
.catch(error => {
console.log(error);
});
25.6.2 例:XMLHttpRequestのPromisify
以下は、イベントベースのXMLHttpRequest APIを介してHTTP GETを実行するPromiseベースの関数です。
function httpGet(url) {
return new Promise(
function (resolve, reject) {
const request = new XMLHttpRequest();
request.onload = function () {
if (this.status === 200) {
// Success
resolve(this.response);
} else {
// Something went wrong (404 etc.)
reject(new Error(this.statusText));
}
};
request.onerror = function () {
reject(new Error(
'XMLHttpRequest Error: '+this.statusText));
};
request.open('GET', url);
request.send();
});
}
httpGet()は次のように使用します。
httpGet('http://example.com/file.txt')
.then(
function (value) {
console.log('Contents: ' + value);
},
function (reason) {
console.error('Something went wrong', reason);
});
25.6.3 例:アクティビティの遅延
setTimeout()をPromiseベースの関数delay()として実装してみましょう(Q.delay()に似ています)。
function delay(ms) {
return new Promise(function (resolve, reject) {
setTimeout(resolve, ms); // (A)
});
}
// Using delay():
delay(5000).then(function () { // (B)
console.log('5 seconds have passed!')
});
A行では、パラメータなしでresolveを呼び出していますが、これはresolve(undefined)を呼び出すことと同じです。B行でもfulfillment値は必要なく、単に無視します。通知されるだけで十分です。
25.6.4 例:Promiseのタイムアウト
function timeout(ms, promise) {
return new Promise(function (resolve, reject) {
promise.then(resolve);
setTimeout(function () {
reject(new Error('Timeout after '+ms+' ms')); // (A)
}, ms);
});
}
タイムアウト後の拒否(A行)はリクエストをキャンセルしませんが、Promiseがその結果でfulfilledされるのを防ぎます。
timeout()は次のように使用します。
timeout(5000, httpGet('http://example.com/file.txt'))
.then(function (value) {
console.log('Contents: ' + value);
})
.catch(function (reason) {
console.error('Error or timeout', reason);
});
25.7 Promiseを作成する他の方法
これで、Promiseの機能を詳しく調べることができます。まず、Promiseを作成するさらに2つの方法を探ってみましょう。
25.7.1 Promise.resolve()
Promise.resolve(x)は次のように動作します。
- ほとんどの値
xに対して、xでfulfilledされるPromiseを返します。Promise.resolve('abc').then(x=>console.log(x));// abc xが、コンストラクタがレシーバであるPromise(Promise.resolve()を呼び出す場合のPromise)の場合、xは変更されずに返されます。constp=newPromise(()=>null);console.log(Promise.resolve(p)===p);// truexがthenableの場合、Promiseに変換されます。thenableの確定は、Promiseの確定にもなります。次のコードはそれを示しています。fulfilledThenableは、文字列'hello'でfulfilledされたPromiseとほぼ同じように動作します。それをPromisepromiseに変換した後、then()メソッドは期待通りに動作します(最終行)。constfulfilledThenable={then(reaction){reaction('hello');}};constpromise=Promise.resolve(fulfilledThenable);console.log(promiseinstanceofPromise);// truepromise.then(x=>console.log(x));// hello
つまり、Promise.resolve() を使用して、任意の値(Promise、thenable、その他)をPromiseに変換できます。実際、これはPromise.all()とPromise.race()によって、任意の値の配列をPromiseの配列に変換するために使用されています。
25.7.2 Promise.reject()
Promise.reject(err) は、err で拒否された Promise を返します。
const myError = new Error('Problem!');
Promise.reject(myError)
.catch(err => console.log(err === myError)); // true
25.8 Promise のチェーン
このセクションでは、Promise のチェーン処理について詳しく見ていきます。メソッド呼び出しの結果は
P.then(onFulfilled, onRejected)
新しい Promise Q です。つまり、Q に対して then() を呼び出すことで、Promise ベースの制御フローを継続できます。
- Q は、
onFulfilledまたはonRejectedが返す値で解決されます。 onFulfilledまたはonRejectedが例外をスローすると、Q は拒否されます。
25.8.1 通常の値で Q を解決する
then() が返す Promise Q を通常の値で解決する場合は、後続の then() を介してその値を取得できます。
asyncFunc()
.then(function (value1) {
return 123;
})
.then(function (value2) {
console.log(value2); // 123
});
25.8.2 thenable で Q を解決する
then() が返す Promise Q を、thenable R で解決することもできます。thenable とは、Promise.prototype.then() のように動作する then() メソッドを持つオブジェクトです。したがって、Promise は thenable です。R で解決する(例:onFulfilled から返す)ということは、Q の「後」に挿入されることを意味します。R の解決は、Q の onFulfilled と onRejected のコールバックに転送されます。ある意味、Q は R になります。
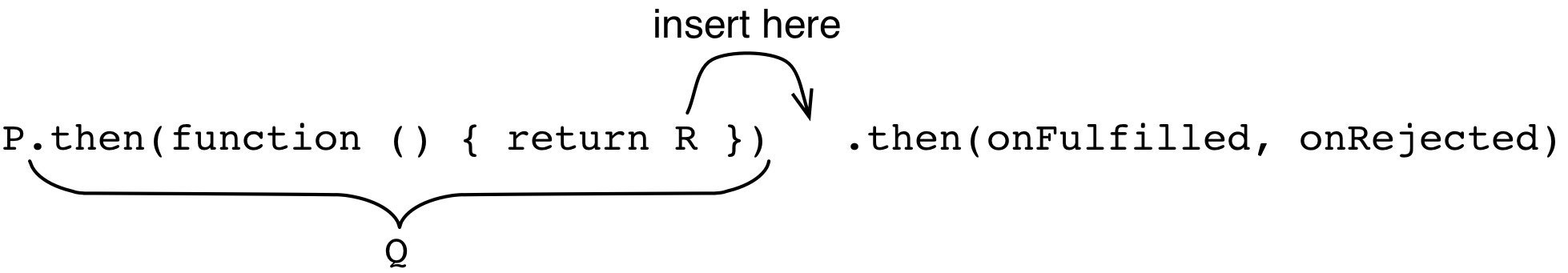
このメカニズムの主な用途は、次の例のようにネストされた then() 呼び出しをフラット化することです。
asyncFunc1()
.then(function (value1) {
asyncFunc2()
.then(function (value2) {
···
});
})
フラット版は次のようになります。
asyncFunc1()
.then(function (value1) {
return asyncFunc2();
})
.then(function (value2) {
···
})
25.8.3 onRejected から Q を解決する
エラーハンドラーで返すものは何でも、解決値(拒否値ではない!)になります。これにより、失敗した場合に使用されるデフォルト値を指定できます。
retrieveFileName()
.catch(function () {
// Something went wrong, use a default value
return 'Untitled.txt';
})
.then(function (fileName) {
···
});
25.8.4 例外をスローして Q を拒否する
then() と catch() のコールバックでスローされた例外は、拒否として次のエラーハンドラーに渡されます。
asyncFunc()
.then(function (value) {
throw new Error();
})
.catch(function (reason) {
// Handle error here
});
25.8.5 チェーンとエラー
エラーハンドラーを持たない then() メソッド呼び出しが1つ以上ある場合があります。その場合、エラーハンドラーがあるまでエラーが渡されます。
asyncFunc1()
.then(asyncFunc2)
.then(asyncFunc3)
.catch(function (reason) {
// Something went wrong above
});
25.9 Promise チェーンの一般的な間違い
25.9.1 間違い:Promise チェーンの末尾を失う
次のコードでは、2つのPromiseのチェーンが構築されますが、その最初の部分のみが返されます。その結果、チェーンの末尾が失われます。
// Don’t do this
function foo() {
const promise = asyncFunc();
promise.then(result => {
···
});
return promise;
}
これは、チェーンの末尾を返すことで修正できます。
function foo() {
const promise = asyncFunc();
return promise.then(result => {
···
});
}
変数promiseが必要ない場合は、このコードをさらに簡素化できます。
function foo() {
return asyncFunc()
.then(result => {
···
});
}
25.9.2 間違い:Promise のネスト
次のコードでは、asyncFunc2() の呼び出しがネストされています。
// Don’t do this
asyncFunc1()
.then(result1 => {
asyncFunc2()
.then(result2 => {
···
});
});
修正するには、最初の then() から2番目の Promise を返し、2番目のチェーンされた then() を介して処理します。
asyncFunc1()
.then(result1 => {
return asyncFunc2();
})
.then(result2 => {
···
});
25.9.3 間違い:チェーン処理の代わりに Promise を作成する
次のコードでは、メソッド insertInto() はその結果に対して新しい Promise を作成します(A 行)。
// Don’t do this
class Model {
insertInto(db) {
return new Promise((resolve, reject) => { // (A)
db.insert(this.fields) // (B)
.then(resultCode => {
this.notifyObservers({event: 'created', model: this});
resolve(resultCode); // (C)
}).catch(err => {
reject(err); // (D)
})
});
}
···
}
よく見ると、結果の Promise は主に、非同期メソッド呼び出し db.insert()(B 行)の解決(C 行)と拒否(D 行)を転送するために使用されていることがわかります。
修正するには、then() を使用してチェーン処理することで、Promise を作成しません。
class Model {
insertInto(db) {
return db.insert(this.fields) // (A)
.then(resultCode => {
this.notifyObservers({event: 'created', model: this});
return resultCode; // (B)
});
}
···
}
説明
resultCode(B 行)を返し、then()によって Promise を作成させます。- Promise チェーン(A 行)を返し、
then()はdb.insert()によって生成された拒否を伝えます。
25.9.4 間違い:エラー処理に then() を使用する
原則として、catch(cb) は then(null, cb) の略記です。しかし、then() の両方のパラメーターを同時に使用すると、問題が発生する可能性があります。
// Don’t do this
asyncFunc1()
.then(
value => { // (A)
doSomething(); // (B)
return asyncFunc2(); // (C)
},
error => { // (D)
···
});
拒否コールバック(D 行)は asyncFunc1() のすべての拒否を受け取りますが、解決コールバック(A 行)によって作成された拒否は受け取りません。たとえば、B 行の同期関数呼び出しで例外がスローされるか、C 行の非同期関数呼び出しで拒否が発生する可能性があります。
したがって、拒否コールバックをチェーンされた catch() に移動する方が良いでしょう。
asyncFunc1()
.then(value => {
doSomething();
return asyncFunc2();
})
.catch(error => {
···
});
25.10 エラー処理のヒント
25.10.1 運用エラーとプログラマーエラー
プログラムには、2種類のエラーがあります。
- 運用エラーは、正しいプログラムが「通常の」アルゴリズムから逸脱する必要がある例外的な状況に遭遇したときに発生します。たとえば、プログラムがデータを書込んでいる間にストレージデバイスのメモリが不足する可能性があります。この種のエラーは予想されます。
- プログラマーエラーは、コードが間違ったことを行うときに発生します。たとえば、関数がパラメーターを文字列にする必要があるのに、数値を受け取る場合があります。この種のエラーは予期せぬものです。
25.10.1.1 運用エラー:拒否と例外を混在させない
運用エラーの場合、各関数はエラーをシグナルするための正確に1つの方法をサポートする必要があります。Promise ベースの関数の場合、それは拒否と例外を混在させないことを意味し、例外をスローしないことを意味します。
25.10.1.2 プログラマーエラー:迅速に失敗する
プログラマーエラーの場合、例外をスローすることで、できるだけ早く失敗することが理にかなっています。
function downloadFile(url) {
if (typeof url !== 'string') {
throw new Error('Illegal argument: ' + url);
}
return new Promise(···).
}
これを行う場合は、非同期コードが例外を処理できることを確認する必要があります。例外をスローすることは、理論的には静的にチェックできる(ソースコードを分析するリンターなどによる)アサーションや同様のものには許容できると考えています。
25.10.2 Promise ベースの関数での例外の処理
then() と catch() のコールバック内で例外がスローされた場合、これら2つのメソッドは例外を拒否に変換するため、問題ではありません。
しかし、同期処理を行うことで非同期関数を開始する場合、状況は異なります。
function asyncFunc() {
doSomethingSync(); // (A)
return doSomethingAsync()
.then(result => {
···
});
}
A 行で例外がスローされると、関数は例外をスローします。この問題には2つの解決策があります。
25.10.2.1 解決策1:拒否された Promise を返す
例外をキャッチして、拒否された Promise として返すことができます。
function asyncFunc() {
try {
doSomethingSync();
return doSomethingAsync()
.then(result => {
···
});
} catch (err) {
return Promise.reject(err);
}
}
25.10.2.2 解決策2:コールバック内で同期コードを実行する
Promise.resolve() を介して then() メソッド呼び出しのチェーンを開始し、コールバック内で同期コードを実行することもできます。
function asyncFunc() {
return Promise.resolve()
.then(() => {
doSomethingSync();
return doSomethingAsync();
})
.then(result => {
···
});
}
別の方法として、Promise コンストラクターを介して Promise チェーンを開始できます。
function asyncFunc() {
return new Promise((resolve, reject) => {
doSomethingSync();
resolve(doSomethingAsync());
})
.then(result => {
···
});
}
このアプローチにより、1ティック節約できます(同期コードはすぐに実行されます)が、コードの規則性が低下します。
25.10.3 さらに読む
このセクションの情報源
- チェーン処理
- Tao of Code の「Promise Anti-patterns」
- エラー処理
- Joyent の「Error Handling in Node.js」
- 「Exploring ES6」Google グループでのユーザー Mörre Noseshine による投稿 はこちら
- Promise ベースの関数から例外をスローしても問題ないかどうかを尋ねるツイートへのフィードバック はこちら
25.11 Promise の合成
合成とは、既存の部分から新しいものを作成することです。Promise のシーケンシャルな合成はすでに経験済みです。2つの Promise P と Q がある場合、次のコードは P が解決された後に Q を実行する新しい Promise を生成します。
P.then(() => Q)
これは、同期コードのセミコロンに似ていることに注意してください。同期操作 f() と g() のシーケンシャルな合成は次のようになります。
f(); g()
このセクションでは、Promise を合成する追加の方法について説明します。
25.11.1 計算を手動でフォークおよび結合する
2つの非同期計算、asyncFunc1() と asyncFunc2() を並行して実行するとします。
// Don’t do this
asyncFunc1()
.then(result1 => {
handleSuccess({result1});
});
.catch(handleError);
asyncFunc2()
.then(result2 => {
handleSuccess({result2});
})
.catch(handleError);
const results = {};
function handleSuccess(props) {
Object.assign(results, props);
if (Object.keys(results).length === 2) {
const {result1, result2} = results;
···
}
}
let errorCounter = 0;
function handleError(err) {
errorCounter++;
if (errorCounter === 1) {
// One error means that everything failed,
// only react to first error
···
}
}
2つの関数呼び出し asyncFunc1() と asyncFunc2() は then() チェーニングなしで行われます。その結果、どちらもすぐにほぼ並行して実行されます。実行はフォークされ、各関数呼び出しによって個別の「スレッド」が生成されます。両方のスレッドが終了すると(結果またはエラーで)、handleSuccess() または handleError() で単一のスレッドに結合されます。
このアプローチの問題は、手動でエラーが発生しやすい作業が多すぎることです。修正するには、組み込みメソッド Promise.all() を使用して、自分で行わないことです。
25.11.2 Promise.all() を使用した計算のフォークと結合
Promise.all(iterable)は、Promiseのイテラブル(thenableおよびその他の値はPromise.resolve()によってPromiseに変換されます)を受け取ります。それらのすべてがfulfilledされると、それらの値の配列でfulfilledされます。iterableが空の場合、all()によって返されるPromiseはすぐにfulfilledされます。
Promise.all([
asyncFunc1(),
asyncFunc2(),
])
.then(([result1, result2]) => {
···
})
.catch(err => {
// Receives first rejection among the Promises
···
});
25.11.3 Promise.all()によるmap()
Promiseの良い点の1つは、Promiseベースの関数は結果を返すため、多くの同期ツールが引き続き機能することです。たとえば、Arrayメソッドのmap()を使用できます。
const fileUrls = [
'http://example.com/file1.txt',
'http://example.com/file2.txt',
];
const promisedTexts = fileUrls.map(httpGet);
promisedTextsはPromiseの配列です。前のセクションで既に説明したPromise.all()を使用して、その配列を結果の配列でfulfilledされるPromiseに変換できます。
Promise.all(promisedTexts)
.then(texts => {
for (const text of texts) {
console.log(text);
}
})
.catch(reason => {
// Receives first rejection among the Promises
});
25.11.4 Promise.race()によるタイムアウト
Promise.race(iterable)は、Promiseのイテラブル(thenableおよびその他の値はPromise.resolve()によってPromiseに変換されます)を受け取り、Promise Pを返します。入力Promiseの中で最初に解決されたものが、その解決状態を出力Promiseに渡します。iterableが空の場合、race()によって返されるPromiseは決して解決されません。
例として、タイムアウトを実装するためにPromise.race()を使用してみましょう。
Promise.race([
httpGet('http://example.com/file.txt'),
delay(5000).then(function () {
throw new Error('Timed out')
});
])
.then(function (text) { ··· })
.catch(function (reason) { ··· });
25.12 2つの有用な追加Promiseメソッド
このセクションでは、多くのPromiseライブラリが提供する、Promiseに関する2つの有用なメソッドについて説明します。これらはPromiseをさらに説明するためだけに示されており、Promise.prototypeに追加しないでください(この種の修正は、ポリフィルによってのみ行う必要があります)。
25.12.1 done()
複数のPromiseメソッド呼び出しをチェーンすると、エラーが暗黙的に破棄されるリスクがあります。たとえば
function doSomething() {
asyncFunc()
.then(f1)
.catch(r1)
.then(f2); // (A)
}
A行のthen()が拒否を生成した場合、どこでも処理されません。PromiseライブラリQは、メソッド呼び出しのチェーンの最後の要素として使用されるdone()メソッドを提供します。これは最後のthen()を置き換え、(1〜2個の引数を持つ)
function doSomething() {
asyncFunc()
.then(f1)
.catch(r1)
.done(f2);
}
または最後のthen()の後に挿入されます(引数は0個)。
function doSomething() {
asyncFunc()
.then(f1)
.catch(r1)
.then(f2)
.done();
}
Qのドキュメントを引用すると
doneとthenの使用に関する黄金律は、Promiseを他の誰かに返すか、チェーンが自分自身で終わる場合は、doneを呼び出して終了させることです。catchで終了しても十分ではありません。なぜなら、catchハンドラー自体がエラーをスローする可能性があるからです。
ECMAScript 6でdone()を実装する方法は次のとおりです。
Promise.prototype.done = function (onFulfilled, onRejected) {
this.then(onFulfilled, onRejected)
.catch(function (reason) {
// Throw an exception globally
setTimeout(() => { throw reason }, 0);
});
};
doneの機能は明らかに有用ですが、ECMAScript 6には追加されていません。最初に、エンジンが自動的にどれだけ検出できるかを調査することが目的でした。それがどの程度うまく機能するかによって、done()を導入する必要がある可能性があります。
25.12.2 finally()
エラーが発生したかどうかに関係なく、アクションを実行したい場合があります。たとえば、リソースの使用が終了した後にクリーンアップするためです。それがPromiseメソッドfinally()の用途であり、例外処理のfinally句と非常によく似ています。そのコールバックは引数を受け取りませんが、解決または拒否のいずれかが通知されます。
createResource(···)
.then(function (value1) {
// Use resource
})
.then(function (value2) {
// Use resource
})
.finally(function () {
// Clean up
});
Domenic Denicolaはこのようにfinally()を実装することを提案しています。
Promise.prototype.finally = function (callback) {
const P = this.constructor;
// We don’t invoke the callback in here,
// because we want then() to handle its exceptions
return this.then(
// Callback fulfills => continue with receiver’s fulfillment or rejec\
tion
// Callback rejects => pass on that rejection (then() has no 2nd para\
meter!)
value => P.resolve(callback()).then(() => value),
reason => P.resolve(callback()).then(() => { throw reason })
);
};
コールバックは、レシーバ(this)の解決方法を決定します。
- コールバックが例外をスローするか、拒否されたPromiseを返す場合、それが拒否値になります。
- それ以外の場合は、レシーバの解決(履行または拒否)が、
finally()によって返されるPromiseの解決になります。ある意味、メソッドのチェーンからfinally()を取り除きます。
例1(Jake Archibaldによる):スピナーを非表示にするためのfinally()の使用。簡略版
showSpinner();
fetchGalleryData()
.then(data => updateGallery(data))
.catch(showNoDataError)
.finally(hideSpinner);
例2(Kris Kowalによる):テストのティアダウンにfinally()を使用。
const HTTP = require("q-io/http");
const server = HTTP.Server(app);
return server.listen(0)
.then(function () {
// run test
})
.finally(server.stop);
25.13 Node.js:コールバックベースの同期関数とPromiseの併用
PromiseライブラリQには、Node.jsスタイルの(err, result)コールバックAPIとのインターフェースのためのツール関数があります。たとえば、denodeifyはコールバックベースの関数をPromiseベースの関数に変換します。
const readFile = Q.denodeify(FS.readFile);
readFile('foo.txt', 'utf-8')
.then(function (text) {
···
});
denodifyは、Q.denodeify()の機能のみを提供し、ECMAScript 6 Promise APIに準拠するマイクロライブラリです。
25.14 ES6互換のPromiseライブラリ
多くのPromiseライブラリが存在します。次のものはECMAScript 6 APIに準拠しているため、現在使用でき、後でネイティブのES6に簡単に移行できます。
最小限のポリフィル
- Jake Archibaldによる「ES6-Promises」は、RSVP.jsからES6 APIのみを抽出します。
- Kyle Simpsonによる「Native Promise Only (NPO)」は、「ネイティブES6プロミスのためのポリフィルであり、厳密な仕様定義にできるだけ近い(拡張機能なし)ものです」。
- Calvin Metcalfによる「Lie」は、「Promises/A+仕様を実装する、小さく、高性能なPromiseライブラリ」です。
大規模なPromiseライブラリ
- Stefan Pennerによる「RSVP.js」は、ES6 Promise APIのスーパーセットです。
- Petka Antonovによる「Bluebird」は、ES2015テスト(Test262)に合格する人気のPromiseライブラリであり、ES6 Promisesの代替手段です。
-
Kris Kowalによる
Q.PromiseはES6 APIを実装しています。
ES6標準ライブラリのポリフィル
- Paul Millrによる「ES6 Shim」には
Promiseが含まれています。 - Babelで使用されているES6+ポリフィルであるDenis Pushkarevによる「core-js」には
Promiseが含まれています。
25.15 次のステップ:ジェネレータによるPromiseの使用
Promiseによる非同期関数の実装は、イベントまたはコールバックによる実装よりも便利ですが、それでも理想的ではありません。
- 非同期コードと同期コードはまったく異なる動作をします。その結果、これらの実行スタイルを混ぜ合わせ、関数またはメソッド間で切り替えることは面倒です。
- 概念的には、非同期関数を呼び出すことはブロッキングコールです。呼び出しを行うコードは、非同期計算中に中断され、結果が得られると再開されます。しかし、コードはこの点を十分に反映していません。
解決策は、ブロッキングコールをJavaScriptに取り込むことです。ジェネレータを使用すると、ライブラリを介してこれを行うことができます。次のコードでは、制御フローライブラリcoを使用して、2つのJSONファイルを非同期的に取得します。
co(function* () {
try {
const [croftStr, bondStr] = yield Promise.all([ // (A)
getFile('https://:8000/croft.json'),
getFile('https://:8000/bond.json'),
]);
const croftJson = JSON.parse(croftStr);
const bondJson = JSON.parse(bondStr);
console.log(croftJson);
console.log(bondJson);
} catch (e) {
console.log('Failure to read: ' + e);
}
});
A行では、Promise.all()の結果が準備できるまで、yieldによって実行がブロック(待機)されます。つまり、非同期操作を実行しながら、コードは同期的に見えます。
ジェネレータに関する章で詳細を説明しています。
25.16 Promiseの詳細:簡単な実装
このセクションでは、別の角度からPromiseにアプローチします。APIの使用方法を学ぶのではなく、簡単な実装を見ていきます。この異なる角度は、Promiseを理解する上で非常に役立ちました。
Promiseの実装はDemoPromiseと呼ばれます。理解しやすくするために、APIと完全に一致するわけではありません。しかし、実際のインプリメンテーションが直面する課題について多くの洞察を与えるのに十分な近さです。
DemoPromiseは、3つのプロトタイプメソッドを持つクラスです。
DemoPromise.prototype.resolve(value)DemoPromise.prototype.reject(reason)DemoPromise.prototype.then(onFulfilled, onRejected)
つまり、resolveとrejectはメソッドです(コンストラクタのコールバックパラメータに渡される関数ではありません)。
25.16.1 スタンドアロンのPromise
最初の実装は、最小限の機能を持つスタンドアロンのPromiseです。
- Promiseを作成できます。
- Promiseを解決または拒否できますが、一度だけ実行できます。
then()を介してリアクション(コールバック)を登録できます。Promiseが既に解決されているかどうかに関係なく、独立して機能する必要があります。- このメソッドはまだチェーンをサポートしていません。何も返しません。
この最初の実装の使用方法を次に示します。
const dp = new DemoPromise();
dp.resolve('abc');
dp.then(function (value) {
console.log(value); // abc
});
次の図は、最初の実装であるDemoPromiseの動作を示しています。
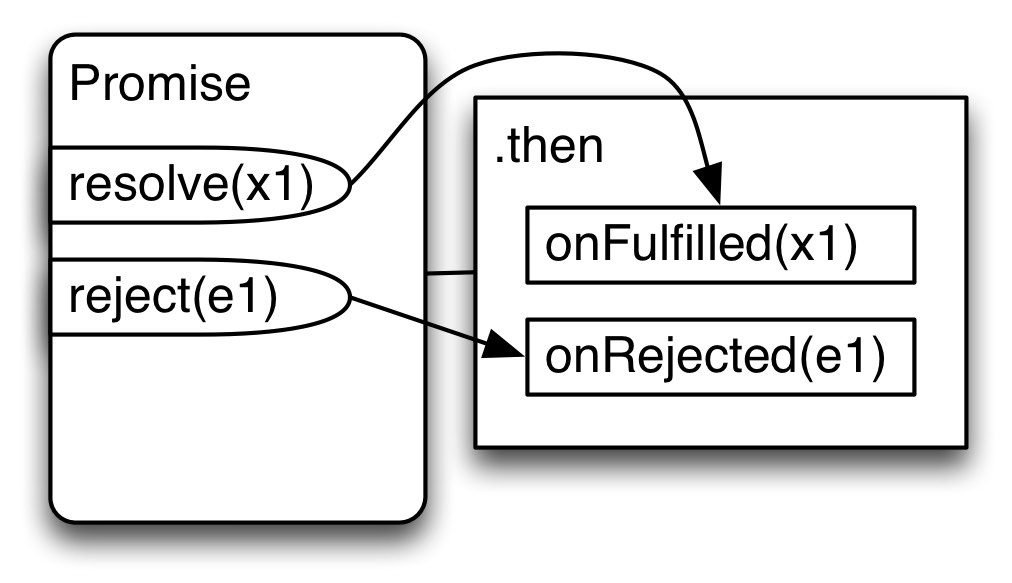
25.16.1.1 DemoPromise.prototype.then()
まずthen()を調べましょう。2つのケースを処理する必要があります。
- Promiseがまだ保留中の場合、Promiseが解決されたときに使用される
onFulfilledとonRejectedの呼び出しをキューに入れます。 - Promiseが既に履行または拒否されている場合、
onFulfilledまたはonRejectedをすぐに呼び出すことができます。
then(onFulfilled, onRejected) {
const self = this;
const fulfilledTask = function () {
onFulfilled(self.promiseResult);
};
const rejectedTask = function () {
onRejected(self.promiseResult);
};
switch (this.promiseState) {
case 'pending':
this.fulfillReactions.push(fulfilledTask);
this.rejectReactions.push(rejectedTask);
break;
case 'fulfilled':
addToTaskQueue(fulfilledTask);
break;
case 'rejected':
addToTaskQueue(rejectedTask);
break;
}
}
前のコードスニペットは、次のヘルパー関数を使用します。
function addToTaskQueue(task) {
setTimeout(task, 0);
}
25.16.1.2 DemoPromise.prototype.resolve()
resolve()は次のように機能します。Promiseが既に解決されている場合、何も行いません(Promiseは一度だけ解決できることを保証します)。それ以外の場合は、Promiseの状態が'fulfilled'に変更され、結果がthis.promiseResultにキャッシュされます。次に、これまでにエンキューされたすべての履行リアクションがトリガーされます。
resolve(value) {
if (this.promiseState !== 'pending') return;
this.promiseState = 'fulfilled';
this.promiseResult = value;
this._clearAndEnqueueReactions(this.fulfillReactions);
return this; // enable chaining
}
_clearAndEnqueueReactions(reactions) {
this.fulfillReactions = undefined;
this.rejectReactions = undefined;
reactions.map(addToTaskQueue);
}
reject()はresolve()に似ています。
25.16.2 チェーン
次に実装する機能はチェーンです。
-
then()は、onFulfilledまたはonRejectedが返すものを解決するPromiseを返します。 onFulfilledまたはonRejectedがない場合、それらが受け取るものthen()によって返されるPromiseに渡されます。
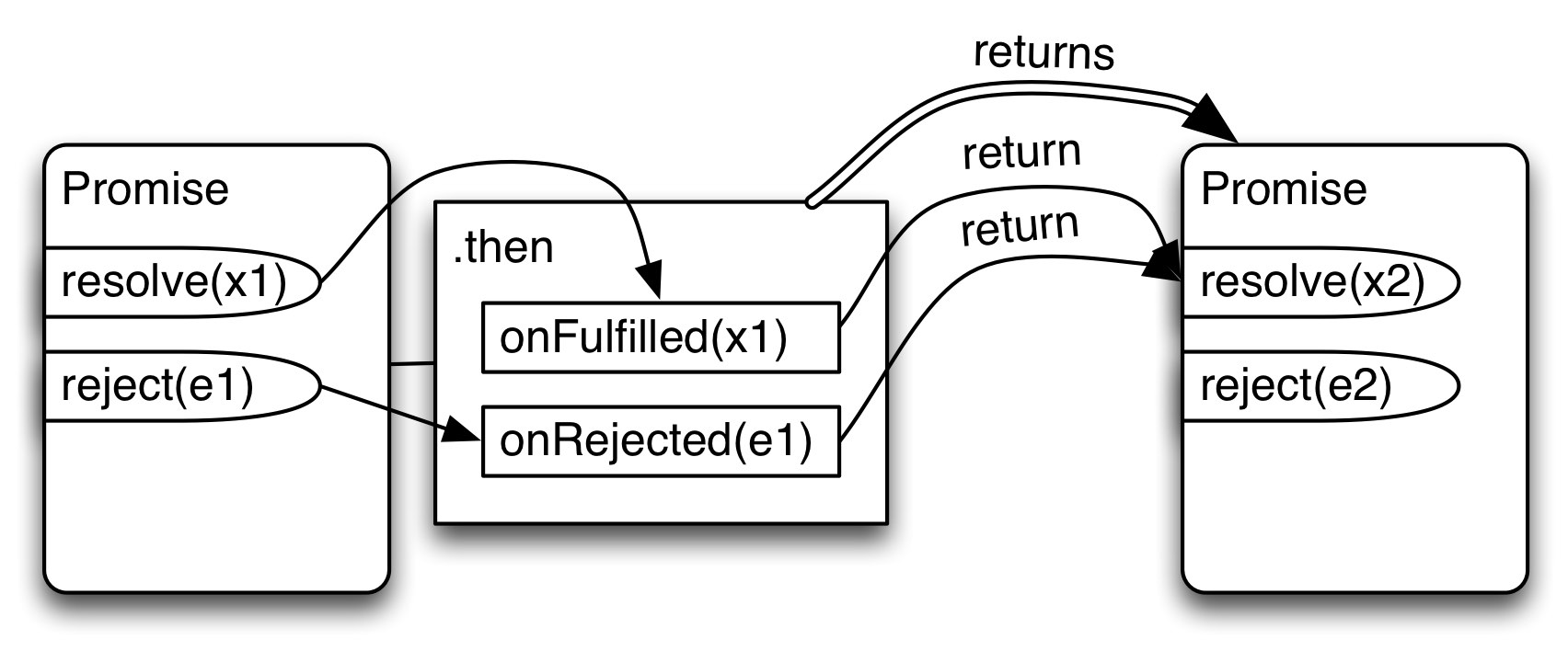
明らかに、変更されるのはthen()だけです。
then(onFulfilled, onRejected) {
const returnValue = new Promise(); // (A)
const self = this;
let fulfilledTask;
if (typeof onFulfilled === 'function') {
fulfilledTask = function () {
const r = onFulfilled(self.promiseResult);
returnValue.resolve(r); // (B)
};
} else {
fulfilledTask = function () {
returnValue.resolve(self.promiseResult); // (C)
};
}
let rejectedTask;
if (typeof onRejected === 'function') {
rejectedTask = function () {
const r = onRejected(self.promiseResult);
returnValue.resolve(r); // (D)
};
} else {
rejectedTask = function () {
// `onRejected` has not been provided
// => we must pass on the rejection
returnValue.reject(self.promiseResult); // (E)
};
}
···
return returnValue; // (F)
}
then()は新しいPromiseを作成し、返します(A行とF行)。さらに、fulfilledTaskとrejectedTaskは異なる方法で設定されます。解決後…
onFulfilledの結果を使用して、returnValueを解決します(B行)。onFulfilledがない場合は、履行値を使用してreturnValueを解決します(C行)。
onRejectedの結果を使用して、returnValueを解決します(拒否しません!)(D行)。onRejectedがない場合は、拒否値をreturnValueに渡します(E行)。
25.16.3 フラット化
フラット化は主に、チェーン処理をより便利にするためのものです。通常、リアクションから値を返すことは、それを次のthen()に渡します。Promiseを返す場合、次の例のように「展開」されると便利です。
asyncFunc1()
.then(function (value1) {
return asyncFunc2(); // (A)
})
.then(function (value2) {
// value2 is fulfillment value of asyncFunc2() Promise
console.log(value2);
});
A行でPromiseを返し、現在のメソッド内にthen()の呼び出しをネストする必要はありませんでした。メソッドの結果に対してthen()を呼び出すことができました。したがって、ネストされたthen()はなく、すべてフラットなままです。
これは、resolve()メソッドにフラット化を行わせることで実装します。
- Promise PをPromise Qで解決することは、Qの解決がPのリアクションに転送されることを意味します。
- PはQに「ロックイン」されます。もはや解決(拒否を含む)できなくなります。そして、その状態と結果は常にQと同じになります。
Qを(Promiseだけでなく)thenableとして許可すると、フラット化をより汎用的にすることができます。
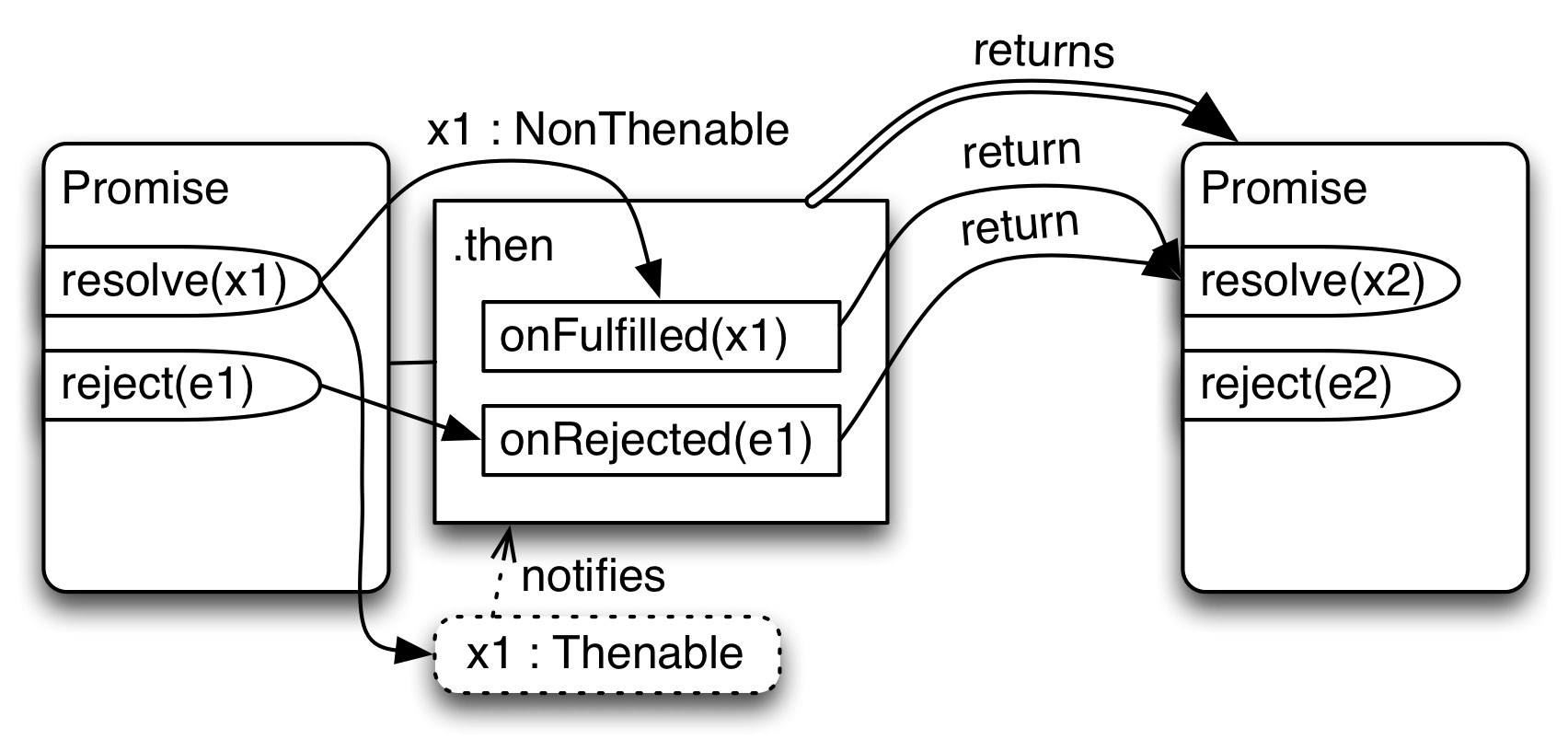
ロックインを実装するために、新しいブール型フラグthis.alreadyResolvedを導入します。これがtrueになると、thisはロックされ、それ以上解決できなくなります。その状態はロックインされているPromiseと同じであるため、thisは依然として保留中である可能性があることに注意してください。
resolve(value) {
if (this.alreadyResolved) return;
this.alreadyResolved = true;
this._doResolve(value);
return this; // enable chaining
}
実際の解決は、プライベートメソッド_doResolve()で行われます。
_doResolve(value) {
const self = this;
// Is `value` a thenable?
if (typeof value === 'object' && value !== null && 'then' in value) {
// Forward fulfillments and rejections from `value` to `this`.
// Added as a task (versus done immediately) to preserve async semant\
ics.
addToTaskQueue(function () { // (A)
value.then(
function onFulfilled(result) {
self._doResolve(result);
},
function onRejected(error) {
self._doReject(error);
});
});
} else {
this.promiseState = 'fulfilled';
this.promiseResult = value;
this._clearAndEnqueueReactions(this.fulfillReactions);
}
}
フラット化はA行で行われます。valueが履行された場合、selfを履行させたいですし、valueが拒否された場合、selfを拒否させたいです。alreadyResolvedによる保護を回避するために、プライベートメソッド_doResolveと_doRejectを介して転送が行われます。
25.16.4 Promiseの状態の詳細
チェーン処理を使用すると、Promiseの状態はより複雑になります(ECMAScript 6仕様の25.4節で説明されているとおり)。
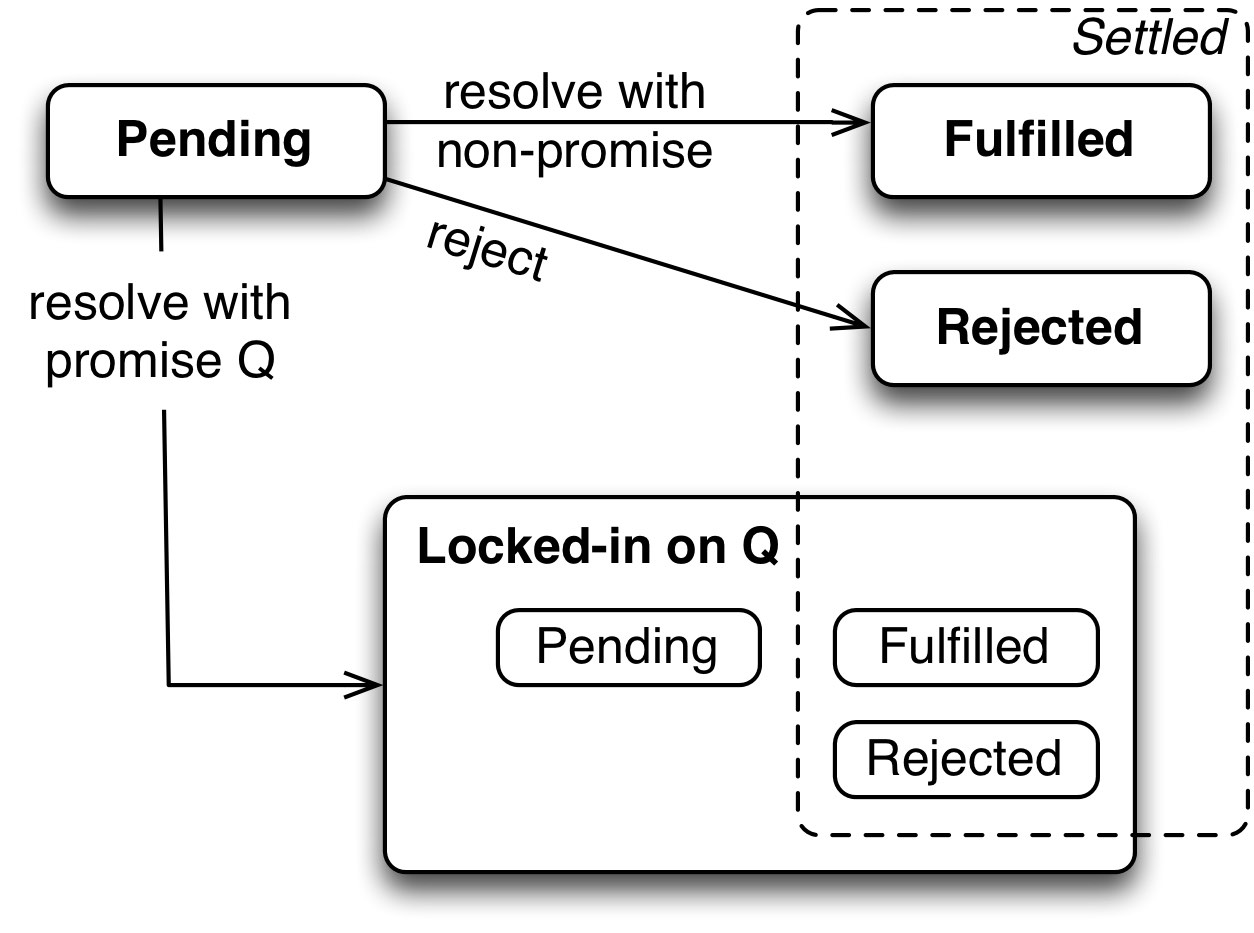
Promiseを使用しているだけの場合は、通常、簡略化された世界観を採用し、ロックインを無視できます。最も重要な状態関連の概念は「解決済み」です。Promiseは、履行されているか拒否されているかのいずれかの場合に解決済みです。Promiseが解決済みになると、それ以上変更されません(状態と履行または拒否値)。
Promiseを実装する場合は、「解決」も重要であり、理解が難しくなります。
- 直感的には、「解決済み」は「(直接)解決できなくなった」ことを意味します。Promiseは、解決済みであるか、ロックインされているかのいずれかの場合に解決済みです。仕様を引用すると、「未解決のPromiseは常に保留状態です。解決済みのPromiseは、保留中、履行済み、または拒否済みのいずれかの状態である可能性があります。」
- 解決は必ずしも解決に結びつくわけではありません。常に保留状態である別のPromiseを使用してPromiseを解決できます。
- 解決には、拒否が含まれるようになりました(つまり、より一般的です)。拒否されたPromiseで解決することで、Promiseを拒否できます。
25.16.5 例外
最後の機能として、ユーザーコードの例外を拒否として処理するPromiseを実装したいと思います。現時点では、「ユーザーコード」とは、then()の2つのコールバックパラメーターを意味します。
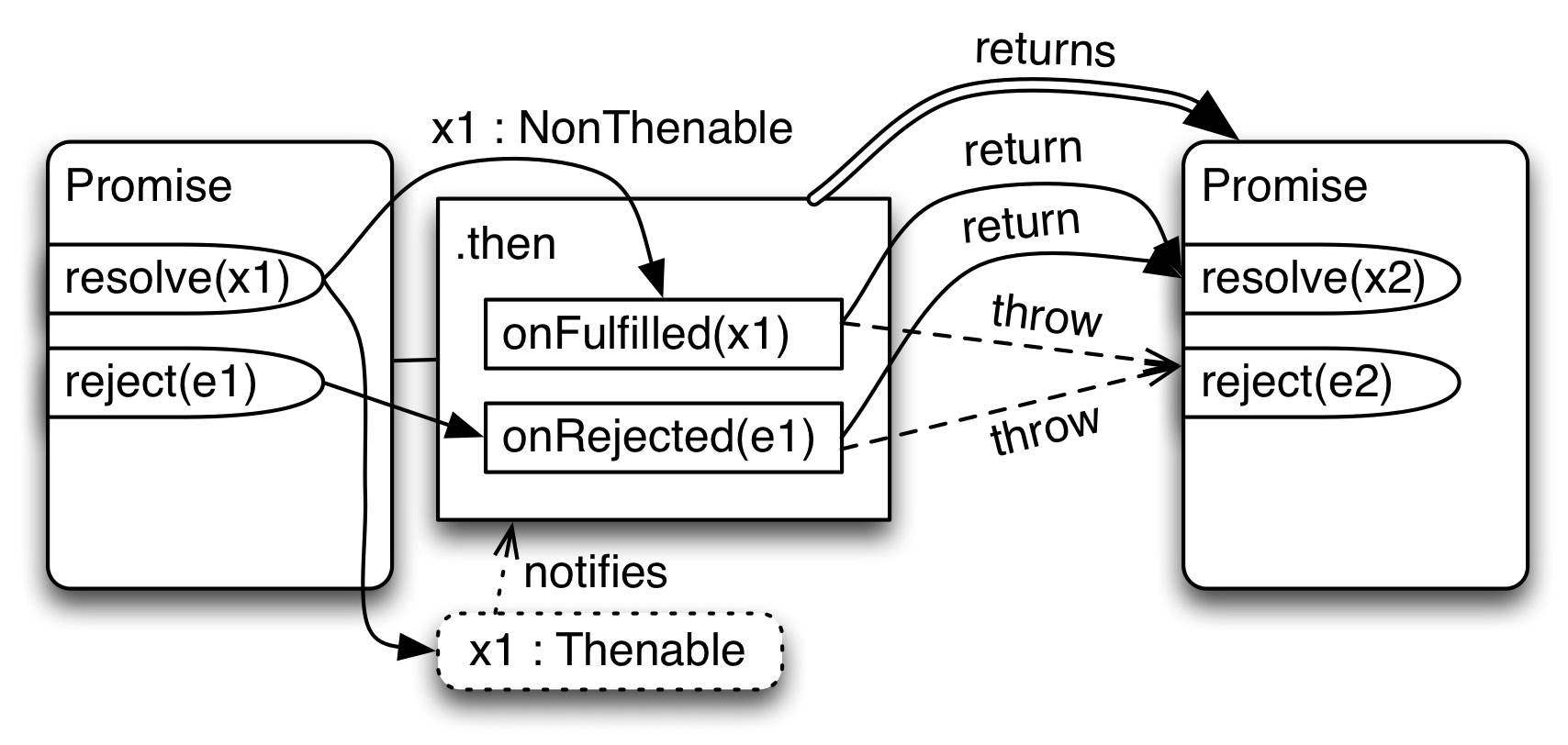
次の抜粋は、A行でその呼び出しの周りにtry-catchをラップすることにより、onFulfilled内の例外を拒否に変換する方法を示しています。
then(onFulfilled, onRejected) {
···
let fulfilledTask;
if (typeof onFulfilled === 'function') {
fulfilledTask = function () {
try {
const r = onFulfilled(self.promiseResult); // (A)
returnValue.resolve(r);
} catch (e) {
returnValue.reject(e);
}
};
} else {
fulfilledTask = function () {
returnValue.resolve(self.promiseResult);
};
}
···
}
25.16.6 公開コンストラクターパターン
DemoPromiseを実際のPromise実装に変換したい場合、公開コンストラクターパターン[2]も実装する必要があります。ES6 Promiseは、メソッドを介してではなく、コンストラクターのコールバックパラメーターであるexecutorに渡される関数によって解決および拒否されます。
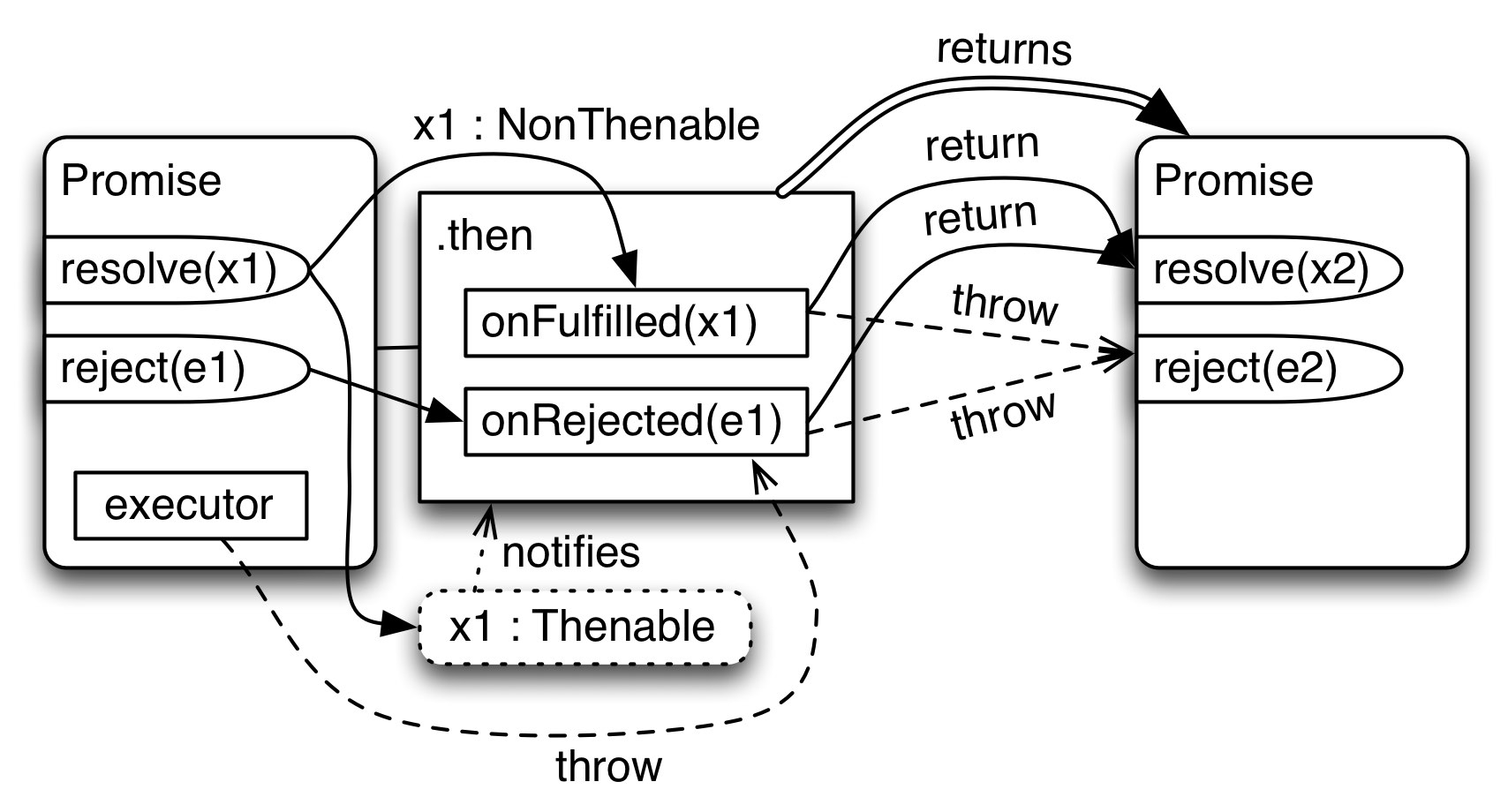
executorが例外をスローした場合、「その」Promiseは拒否される必要があります。
25.17 Promiseの長所と短所
25.17.1 Promiseの長所
25.17.1.1 非同期APIの統一
Promiseの重要な利点の1つは、非同期ブラウザAPIでますます使用されるようになり、現在多様で互換性のないパターンと規約を統一することです。2つの今後のPromiseベースのAPIを見てみましょう。
Fetch APIは、XMLHttpRequestに代わるPromiseベースの代替手段です。
fetch(url)
.then(request => request.text())
.then(str => ···)
fetch()は実際の要求に対するPromiseを返し、text()は文字列としてコンテンツに対するPromiseを返します。
プログラムによるモジュールのインポートのためのECMAScript 6 APIもPromiseに基づいています。
System.import('some_module.js')
.then(some_module => {
···
})
25.17.1.2 Promise対イベント
イベントと比較して、Promiseは一括結果の処理に適しています。結果を計算する前または後に結果に登録するかどうかは関係なく、結果を取得します。Promiseのこの利点は本質的に重要です。一方で、繰り返し発生するイベントの処理には使用できません。チェーン処理はPromiseのもう1つの利点ですが、イベント処理に追加できるものです。
25.17.1.3 Promise対コールバック
コールバックと比較して、Promiseはよりクリーンな関数(またはメソッド)シグネチャを持っています。コールバックでは、パラメーターが入力と出力に使用されます。
fs.readFile(name, opts?, (err, string | Buffer) => void)
Promiseでは、すべてのパラメーターが入力に使用されます。
readFilePromisified(name, opts?) : Promise<string | Buffer>
その他のPromiseの利点としては、以下があります。
- 非同期エラーと通常の例外の両方を統一的に処理します。
Array.prototype.map()などの同期ツールを再利用できるため、合成が容易になります。then()とcatch()のチェーン処理。- コールバックを複数回通知するのを防ぎます。一部の開発環境では、処理されない拒否についても警告が表示されます。
25.17.2 Promiseが常に最良の選択肢とは限らない
Promiseは、単一の非同期結果に適しています。以下には適していません。
- 繰り返し発生するイベント:これに関心がある場合は、通常のイベント処理に巧妙なチェーン処理を追加するリアクティブプログラミングをご覧ください。
- データストリーム:これらをサポートするための標準が現在開発中です。
ECMAScript 6 Promiseには、場合によっては便利な2つの機能がありません。
- キャンセルできません。
- 進行状況(例:クライアント側のユーザーインターフェースにプログレスバーを表示する)を問い合わせることはできません。
Q Promiseライブラリは後者に対するサポートがあり、Promises/A+に両方の機能を追加する計画があります。
25.18 参照:ECMAScript 6 Promise API
このセクションでは、仕様で説明されているECMAScript 6 Promise APIの概要を示します。
25.18.1 Promiseコンストラクター
Promiseのコンストラクターは、次のように呼び出されます。
const p = new Promise(function (resolve, reject) { ··· });
このコンストラクターのコールバックは、executorと呼ばれます。executorは、そのパラメーターを使用して新しいPromisepを解決または拒否できます。
-
resolve(x)はxでpを解決します。xがthenableである場合、その解決はpに転送されます(then()を介して登録されたリアクションのトリガーが含まれます)。- それ以外の場合、
pはxで履行されます。
-
reject(e)は、値e(多くの場合、Errorのインスタンス)でpを拒否します。
25.18.2 静的Promiseメソッド
25.18.2.1 Promiseの作成
次の2つの静的メソッドは、レシーバーの新しいインスタンスを作成します。
-
Promise.resolve(x):Promiseを認識して、任意の値をPromiseに変換します。xのコンストラクターがレシーバーである場合、xは変更されずに返されます。- それ以外の場合、
xで履行されるレシーバーの新しいインスタンスを返します。
-
Promise.reject(reason):値reasonで拒否されるレシーバーの新しいインスタンスを作成します。
25.18.2.2 Promiseの合成
直感的には、静的メソッドPromise.all()とPromise.race()は、Promiseのiterableを単一のPromiseに合成します。つまり、
- iterableを取得します。iterableの要素は、
this.resolve()を介してPromiseに変換されます。 - 新しいPromiseを返します。そのPromiseは、レシーバーの新しいインスタンスです。
メソッドは以下のとおりです。
-
Promise.all(iterable):…なPromiseを返します。iterable内のすべての要素が履行された場合に履行されます。
履行値:履行値を含む配列。- 要素のいずれかが拒否された場合に拒否されます。
拒否値:最初の拒否値。
-
Promise.race(iterable):解決されたiterableの最初の要素を使用して、返されたPromiseが解決されます。
25.18.3 Promise.prototypeメソッド
25.18.3.1 Promise.prototype.then(onFulfilled, onRejected)
- コールバック関数
onFulfilledとonRejectedは、リアクションと呼ばれます。 -
Promiseが既にFulfilled状態である場合、またはFulfilled状態になった時点で、
onFulfilledがすぐに呼び出されます。同様に、onRejectedはRejectionを通知されます。 -
then()は、新しいPromise Q(レシーバのコンストラクタの種別を使用して作成)を返します。- リアクションのいずれかが値を返す場合、Qはそれによって解決されます。
- リアクションのいずれかが例外をスローした場合、Qはそれによって拒否されます。
- 省略されたリアクション
onFulfilledが省略されている場合、レシーバのFulfillmentはthen()の結果に転送されます。onRejectedが省略されている場合、レシーバのRejectionはthen()の結果に転送されます。
省略されたリアクションのデフォルト値は、次のように実装できます。
function defaultOnFulfilled(x) {
return x;
}
function defaultOnRejected(e) {
throw e;
}
25.18.3.2 Promise.prototype.catch(onRejected)
-
p.catch(onRejected)は、p.then(null, onRejected)と同じです。
25.19 さらに読む
[1] Brian CavalierとDomenic Denicolaによって編集された“Promises/A+”(JavaScript Promisesの事実上の標準)
[2] Domenic Denicolaによる“The Revealing Constructor Pattern”(このパターンはPromiseコンストラクタで使用されています)